|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
 平成22年7月22日、札幌市のかでる2・7で、北海道、北海道教育委員会、北海道警察本部、
財団法人北海道青少年育成協会、第60回“社会を明るくする運動”北海道推進委員会の主催に
より「青少年の非行・被害防止」道民総ぐるみ大会が開催されました。
今年度から、国において福祉犯罪の被害防止も重点課題に加え、
7月の強調月間の名称が変更したことから、大会名称も併せて変更し“被害”を追加しています。
平成22年7月22日、札幌市のかでる2・7で、北海道、北海道教育委員会、北海道警察本部、
財団法人北海道青少年育成協会、第60回“社会を明るくする運動”北海道推進委員会の主催に
より「青少年の非行・被害防止」道民総ぐるみ大会が開催されました。
今年度から、国において福祉犯罪の被害防止も重点課題に加え、
7月の強調月間の名称が変更したことから、大会名称も併せて変更し“被害”を追加しています。また、今年もかでる内の展示ホールにおいて、パネル展も開催されました。  この日は、主催者として多田道副知事、小津札幌高等検察庁検事長、髙橋道教育委員会教育長、
殿川道警察本部長、遠藤道地方更生保護委員会委員長、藤本道地方保護司連盟会長、
穴田道地方更生保護女性連盟副会長、佐々木道青少年育成協会会長が出席しました。
この日は、主催者として多田道副知事、小津札幌高等検察庁検事長、髙橋道教育委員会教育長、
殿川道警察本部長、遠藤道地方更生保護委員会委員長、藤本道地方保護司連盟会長、
穴田道地方更生保護女性連盟副会長、佐々木道青少年育成協会会長が出席しました。来賓としては、北海道議会から環境生活委員会の遠藤委員と須田委員にご出席をいただきました。 |
 はじめに、 藤本道地方保護司連盟会長の開会宣言により大会の幕が上がりました。
次に、主催者を代表して、多田副知事から挨拶があり
「様々な困難を抱える青少年へ手をさしのべる“勇気”と“優しさ”が必要」と観衆に
呼びかけ、続いて来賓の遠藤道議会環境生活委員が代表して挨拶を頂戴し
「青少年が夢と希望を持つことができる北海道を目指し、関係機関と連携を図りながら、
全力を挙げて努力していく」と決意を述べました。
はじめに、 藤本道地方保護司連盟会長の開会宣言により大会の幕が上がりました。
次に、主催者を代表して、多田副知事から挨拶があり
「様々な困難を抱える青少年へ手をさしのべる“勇気”と“優しさ”が必要」と観衆に
呼びかけ、続いて来賓の遠藤道議会環境生活委員が代表して挨拶を頂戴し
「青少年が夢と希望を持つことができる北海道を目指し、関係機関と連携を図りながら、
全力を挙げて努力していく」と決意を述べました。 |
|
次に、小津札幌高等検察庁検事長から第60回“社会を明るくする運動”に当たっての
法務大臣メッセージ、殿川道警察本部長から非行防止メッセージがそれぞれ紹介されました。 前半の最後には、髙橋道教育委員会教育長が「大会宣言」を提案し、 満場一致で採択されました。 大会の後半は、中学校の国語の先生を経て、現在、詩画作家として活躍し、 講演活動も行っている、坂本 勤氏を迎え、演題「子どもの心を守る」についての 講演が行われました。  坂本氏は、「サイ」を減らすという話からはじめ、私たちは、子どもに「~しなサイ」と
いう言葉を多く使っている。大人は皆「早く起きなさい、勉強しなさい、早く食べなさい、
テレビ見るのやめなさい、あの子と友達になるのやめなさい」など、普段から多くの
「~サイ」を使っており、言われた子どもは、硬い硬い鎧を着て、
自分の殻にこもるようになってしまう。鎧を一度着てしまうと、
脱がす事が不可能になる。体にピッタリくっついてしまい、やさしさも硬い鎧にさえぎられ、
伝わっていかなく、周りの声もほとんど届かなくなる。なので、親は「サイ」を減らし、
自分を主語にし、「お母さん、勉強したらいいと思うな」というように話しかけるようにする。
また親は、「サイ」の鎧をつけないために、間違った「サイ」を言ったら子どもに謝る。
1日に1度は、目を合わせて笑顔を見せる。そうすれば、子ども達はほかの「サイ」を
受け入れてくれるようになると力強く聴衆に訴えました。
坂本氏は、「サイ」を減らすという話からはじめ、私たちは、子どもに「~しなサイ」と
いう言葉を多く使っている。大人は皆「早く起きなさい、勉強しなさい、早く食べなさい、
テレビ見るのやめなさい、あの子と友達になるのやめなさい」など、普段から多くの
「~サイ」を使っており、言われた子どもは、硬い硬い鎧を着て、
自分の殻にこもるようになってしまう。鎧を一度着てしまうと、
脱がす事が不可能になる。体にピッタリくっついてしまい、やさしさも硬い鎧にさえぎられ、
伝わっていかなく、周りの声もほとんど届かなくなる。なので、親は「サイ」を減らし、
自分を主語にし、「お母さん、勉強したらいいと思うな」というように話しかけるようにする。
また親は、「サイ」の鎧をつけないために、間違った「サイ」を言ったら子どもに謝る。
1日に1度は、目を合わせて笑顔を見せる。そうすれば、子ども達はほかの「サイ」を
受け入れてくれるようになると力強く聴衆に訴えました。
|
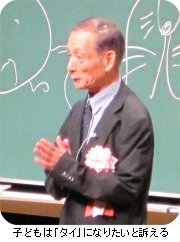 次に、子どもは「タイ」になりたがっていると述べ、自分で考えたい、自分で決めたい、
のんびりしたいと思っている。
つまり、お母さん方も、自分で決められる子ども、自分で考えられる子どもにしたいと思っている
と思う。 また、親は子どもを頑張らせるのではなく「そのままでいい、いや、そのままがいい」
と1年に1回でいいので言ってあげてほしい。そして、命の大切さを伝えるには、
まだ使える物を子どもの前でポンポン捨てる姿を見せない方がいいと訴えました。
次に、子どもは「タイ」になりたがっていると述べ、自分で考えたい、自分で決めたい、
のんびりしたいと思っている。
つまり、お母さん方も、自分で決められる子ども、自分で考えられる子どもにしたいと思っている
と思う。 また、親は子どもを頑張らせるのではなく「そのままでいい、いや、そのままがいい」
と1年に1回でいいので言ってあげてほしい。そして、命の大切さを伝えるには、
まだ使える物を子どもの前でポンポン捨てる姿を見せない方がいいと訴えました。最後に、詩を朗読して、子ども達の「タイ」になりたい気持ちを大事にしていってほしいと述べ、 講演を締めくくりました。 |
 次に、活動事例発表として、社会福祉法人北海道家庭学校の加藤正男校長が
「北海道家庭学校の生活」と題し発表しました。
次に、活動事例発表として、社会福祉法人北海道家庭学校の加藤正男校長が
「北海道家庭学校の生活」と題し発表しました。加藤校長は、1つ1つの寮に夫婦の職員が住み込み、生徒たちと共に1つの屋根の下で生活し、 寮母さんと毎晩、語らいながら炊事をしたり、寮長先生と寮ごとの畑や除雪作業を 協働したりすることで、生徒たちは責任を果たすことの大切さ、厳しさとその喜びを学んでいると 発表されました。 最後に佐々木道青少年育成協会会長が閉会宣言を行い、大会の幕を閉じました。 |